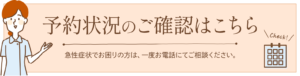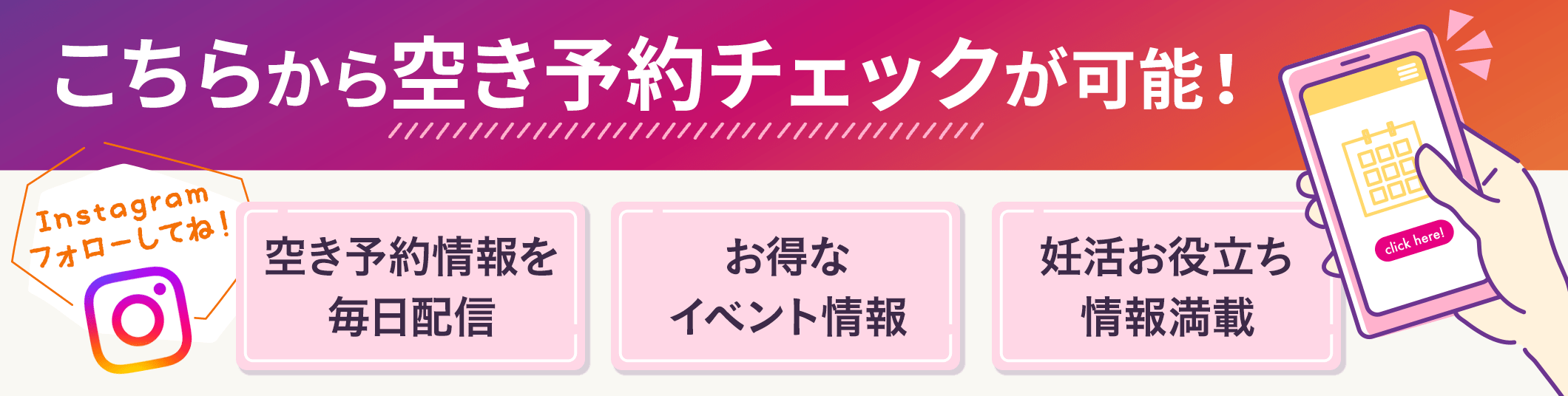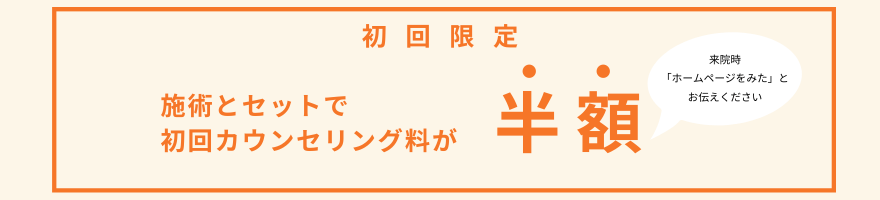東京都江東区にある不妊専門鍼灸院の住吉鍼灸院です。
今回は睡眠障害についてお話しさせて頂きます。
皆さんは常に朝すっきり起きることができていますでしょうか?
また、夜なかなか寝付けないことはないでしょうか。
最近は気温の上昇と湿度の高さにより、エアコンをつけないと寝苦しく起きてしまう夜もあるというお声を当院の患者さまの中からもよく耳にします。
人間の3大欲求の中の1つである睡眠について一緒に見ていきましょう!
睡眠障害(不眠症)とは
簡単に説明すると昼間は活動していて 夜の睡眠に問題があり、そのことで日常生活に影響が出ることを言います。
「眠れない」ということだけではなく「途中で起きてしまう」「朝早く目が覚めてしまう」ということも睡眠障害になり日常に支障をきたすことがあります。
睡眠障害になる原因とは

原因は人それぞれ異なります。
主な原因としては 「ストレス」「生活習慣の乱れ」「薬の影響」などがあげられます。
これらのことで睡眠に関わるホルモンのバランスが乱れてしまい睡眠障害につながります。
特に、「生活習慣の乱れ」のなかには、環境も影響します。
最近でいえば、夜が暑く寝付けない。冬であれば、寒くて寝付けないなど環境によっても睡眠は大きく影響します。その環境が変わるだけでも眠るための機能が低下するため睡眠が妨げられてしまいます。
睡眠障害の主な症状
主な症状をお伝えいたします。
・なかなか寝付けないと感じる
・夜中に何度も目が覚めてしまう
・集中力が続かない
初期の症状では倦怠感や抑うつ感、頭痛や眩暈なども症状として現れます。
1分でできる睡眠障害セルフチェック
適切な診断を受けるには医療機関を受診して頂くと良いと思います。
ここでは1分で出来る睡眠障害の簡単なセルフチェックですので是非やってみてください
・寝付くまでに時間がかかると感じることがある
・夜何度も起きてしまい、その後眠ることが出来ない
・朝は起きたい時間より早く起きてしまい、その後も眠る事が出来ない
・夜は眠りが浅く、ぐっすり眠ったように感じない
・日中、集中力が低下して仕事に支障が出ている
・日中に眠くなることがある
皆さまはいくつ当てはまりましたか?
もし1つでも当てはまった方は睡眠障害の可能性があります。
病院での治療の他に、ご自身でも生活習慣を見直す事や身体をメンテナンスしていく事が重要です。
睡眠障害の種類
睡眠障害には4つのタイプがあります
1、入眠困難
中々寝付けず、寝つきが悪くなったと感じるタイプです。
一般的に消灯してから30分以内程度で入眠すると言われております。
ただし、ベッドに入ってから眠りにつくまでには個人差があります。
また眠りにつけないことをどのくらい苦痛に感じるのかも人それぞれです。
日本睡眠学会では「寝付くまでの時間が普段より2時間以上多くかかる状態」を入眠障害と定義しています。
これは、あくまでも目安ですので、1番の基準は「本人が苦痛や支障を感じているか」という事になります。
2、 中途覚醒
夜中、明け方に何度も目が覚めてしまうタイプです。
健康状態の方でも夜中に1度は目が覚めることはあります。
例えば、夏の暑さや冬の寒さ、騒音など睡眠を妨げる原因があるものに関しては睡眠障害の分類に分けることはありません。
しかし、その後に精神的な焦り、不安感を感じ、再度入眠出来ないとなると中途覚醒分類になります。
また、環境の変化がない状態で1晩に2回以上目が覚めてしまうことも中途覚醒の分類になります。
3、早朝覚醒
目が覚める時間がいつもより早くなり、その後入眠が出来ないタイプです。
年齢と共に起床時間が早くなることはありますが、 体が疲れているのに早く目覚めてしまう、休みたいと感じているのに目がさえてしまい眠れなくなると感じる場合には 早朝覚醒に分類されます。
ただし、生活リズムなどは人それぞれによりますので自分自身が「目覚めたい時間の2時間以上前に起きてしまいその後眠れずに 困っている」という状態が基準になります。
4、熟眠障害
いつもと同じように睡眠時間は確保しているはずなのに、身体の疲れがとれていないように感じるタイプです。
より良い睡眠というのは「睡眠の質」と「適切な睡眠時間」によって決まります。
熟眠障害の方は主に「睡眠の質」が低下した事により疲れがとれないように感じます。 長い睡眠時間を確保しても疲れがとれないと感じる方は熟眠障害に分類されます。
ホルモンとの関係
睡眠にはホルモンが大きく関係しています。
皆さまの中にも「体内時計」という言葉を一度は耳にしたことがあるのではないでしょうか。
それは睡眠に関わるホルモンが働いていることで朝は目が覚め、夜には眠気がくるというものになります。
睡眠には主に「セロトニン」と「メラトニン」というホルモンが関係しています。
日中にはセロトニンの分泌量が増えて、夜になるとメラトニンの分泌量が増えます。 セロトニンは脳から分泌されるホルモンでメラトニンの材料になります。
メラトニンは朝起きて日の光などが目に入ってから14〜16時間後に脳の松果体(しょうかたい)から分泌されて心身をリラックスさせ、自然な睡眠を促す働きがあります。
セロトニンは日光を浴びることで分泌が促されますので、日中に日光を浴びる事も質の高い睡眠を取るのに効果的です。
質の高い睡眠をとるためにはこの二つのホルモンのバランスを保つことが重要であり、睡眠障害に大きく関係をしています。
クリニックでの一般的な治療法
ここでは簡単にクリニックの一般的な治療法をお伝えいたします。
1、睡眠薬を使用した薬物治療
睡眠薬を使用した薬物療法には ベンゾジアゼピン系と非ベンゾジアゼピン系があり、他にも種類があります。
またベンゾジアゼピン系の中でも作用する時間によってタイプが大きく 4 つに分けられています。
もっと詳しい内容を知りたい方は下記の URL の銀座心療内科クリニックをご参照下さい。
参照
銀座心療内科クリニック:睡眠障害(不眠症)の治療方法|銀座心療内科クリニック (ginza-pm.com)
2、認知行動療法
認知行動療法とは ストレスで固まってしまい狭くなってしまった考えや行動を、自分自身の力で柔らかく解きほぐしていきます。
そして、自由に考えたり行動したりする事をお手伝いする心理療法になります。
現在は教育やスポーツなどにも取り入れられている考え方です。
当院の鍼灸治療によるアプローチ法

ここでは当院の鍼灸治療でのアプローチ方法をご紹介いたします。
1、自律神経の乱れを整える
自律神経でも副交感神経の時に入眠がしやすくなります。
ですが、睡眠障害の方は入眠時に交感神経が優位になり、副交感神経を優位にならないことから睡眠に問題が出やすいので鍼灸治療で副交感神経優位になるよう施術を行なっています。
脊際と言われる背骨の際(きわ)は自律神経が多く集まっている部分になりますのでこの部分に刺激を与えることで副交感神経優位になりやすく効果的です。
自律神経を整える経穴(ツボ)への刺鍼や首にある「星状神経節」にレーザーを照射して副交感神経の働きを助けて自律神経を整え正常にホルモンが分泌されるよう に施術を行います。
2、筋肉の弛緩や血流改善を促す
メラトニンやセロトニンのホルモンを運んでいるのは血液になります。
その為、筋肉が硬くなると血流が悪くなり、ホルモンも働きかけたい細胞に到達しにくくなります。
鍼灸では表面の筋肉だけではなく、深部にある筋肉の硬さにもアプローチが出来るため血流の改善を促すことができ、ホルモンバランスが整い、睡眠の質が良くなります。
自宅でも出来るセルフケア
自宅でも出来る簡単なセルフケアの「セロトニン活性法」についてお伝えいたします。
肩甲骨を回して、脳内神経伝達物質の1つでもある「セロトニン」の分泌を増やす運動です。
【やり方】
肩を前回し、後ろ回し、身体を左右へのひねりを入れて行う運動を分けて行います。
回数は前回し15回、後ろ回し15回、左右へのひねり30回を1セットとします。
これを朝昼夜それぞれで行うと効果的です。
睡眠障害(不眠症)のまとめ
睡眠障害(不眠症)は誰にでも起こりうる事で原因は人によって異なります。
また症状やタイプなども人によって変わります。
ただ、どのタイプでも「睡眠の質」を高めていくことが1番の改善方法になります。
特に現代であれば、スマートフォンなどもブルーライトでも睡眠の質は低下します。
ストレスが多くかかる現代社会において、多くの方が少なからず睡眠について悩みを抱えています。
人は睡眠を欠かすことはできません。眠れないことで死に至る事もあります。
睡眠で悩む方が一人でも減り、仕事や趣味を楽しむ事ができると嬉しいなと感じます。
睡眠でお悩みの方は1度当院にご相談くださいませ。
予約状況はこちらになります↓
ただいま、たくさんのご予約をいただいており新規ご予約が取りにくい状況でございます。急性症状でお困りの方は一度お電話でご相談ください。
また施術を受ける前のご相談を公式LINEにて承っておりますので、こちらもどうぞご利用ください。
【監修】
住吉鍼灸院 院長 藤鬼 千子
鍼灸師・あん摩マッサージ指圧師
2011年国家資格はり灸師、あん摩マッサージ指圧師免許取得。 2011年住吉鍼灸院入社。 2017年不妊カウンセリング学会認定、不妊カウンセラー。
施術歴13年